
音声と文字で解説するので、お好みの方でどうぞ!!
>>音声はこちらから(stand.fmにリンクします)
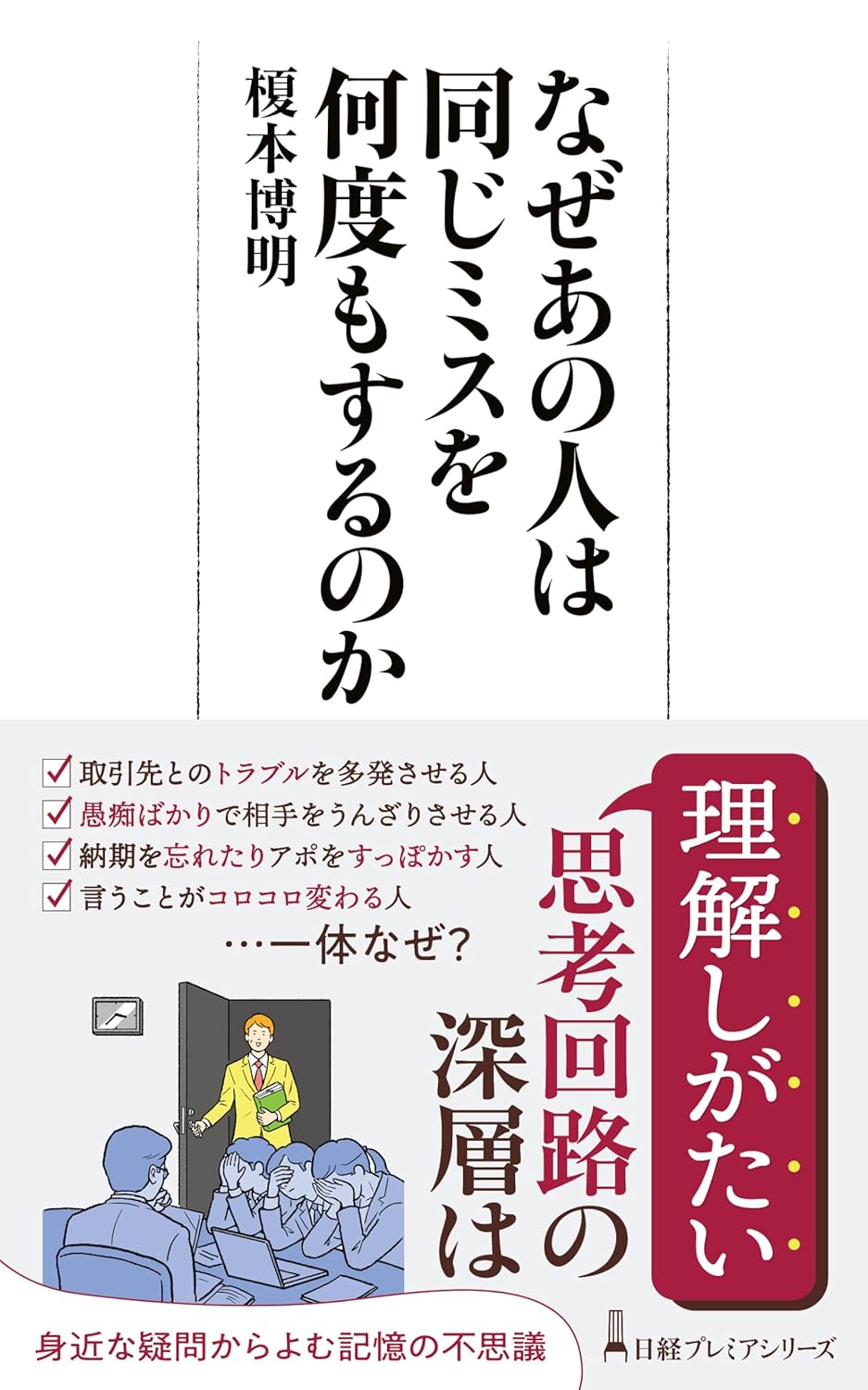
こんにちは!かんのです。
今回ご紹介する本は、榎本博明(えのものひろあき)さんが書かれた、『なぜあの人は同じミスを何度もするのか 』です。

なぜか同じミスを繰り返してしまうあの人、(私もちょっとドキッとしている)の理由に迫ります!
『なぜあの人は同じミスを何度もするのか』を読んで考えた、経営者の「人の扱い方」
『なぜあの人は同じミスを何度もするのか』を読みました。
タイトルだけ見ると「注意しても直らない人をどうするか?」というマネジメント本のように感じますが、実際はもっと深い。
「人間の脳と記憶の限界をどう理解し、どう向き合うか」を教えてくれる本でした。
「注意しても変わらない」のは、性格ではなく“脳の仕組み”
経営をしていると、「何度言っても同じミスをする人」に出会います。
言葉では「次は気をつけます」と言っていても、また同じことを繰り返す。
つい「やる気がない」「意識が低い」と判断してしまいがちです。
しかしこの本では、それを人間の脳の構造”として説明しています。
脳は「記憶の保存」と「再生」を繰り返すうちに情報を歪めていく。
つまり、「聞いたつもり」「伝えたつもり」「覚えたつもり」という“つもり”のズレが自然に起きるのです。
そう考えると、注意や叱責で変えようとすること自体が、根本的なズレなのだと気づかされます。
ミスを責めるより、「仕組み」を変える
私自身、経営者としてチームを見ていて感じるのは、「人の記憶に頼る運用」ほど危ういものはないということです。
同じミスを繰り返すのは、個人の能力ではなくシステムが“忘れる前提”になっていないから。
この本を読んでから、私は「人の脳を信用しすぎない仕組みづくり」を意識するようになりました。
・口頭ではなく、書面・チャットに残す
・言葉より図解・マニュアルで共有する
・1回の説明ではなく、定期的に“思い出させる”設計を入れる
人間の記憶には限界がある。
だからこそ、仕組みで人を助けるのが経営者の仕事なのだと改めて感じました。
実際に「報告の仕組み」を変えてみた
私の会社でも、「報告」に関する仕組みを改善したことがあります。
以前は“記録が苦手なスタッフ”に報告書作成をお願いしていたのですが、どうしても抜け漏れや記載ミスが起こっていました。
そこで思い切って担当を記録が得意なスタッフにチェンジし、あわせて報告書のフォーマットも見直しました。
単なる業務記録ではなく、
「うまくいったこと」「嬉しかったこと」「次に挑戦したいこと」
といった前向きな視点で書けるテンプレートに変えたのです。
すると不思議なことに、報告の質が上がるだけでなく、打ち合わせの時間が週に4時間も短縮されました。
つまり、仕組みを変えるだけで、ミスを責めることなく生産性が上がったのです。
この経験を通じて、「人を変えるより、環境を変える」ことの大切さを実感しました。
経営とは、記憶のズレを埋める仕事
本書を読みながら、経営とは「人の思い込み」と「記憶のズレ」をどう扱うかの連続だと感じました。
伝えたつもり、聞いたつもり、わかったつもり——それらの“つもり”の誤差を放置すると、組織は確実に崩れます。
だからこそ、経営者は「伝えた内容」ではなく、「伝わった結果」に責任を持たなければならない。
これはシンプルですが、非常に難しい課題です。
まとめ
『なぜあの人は同じミスを何度もするのか』は、「人を責めないための知恵」が詰まった一冊でした。
人のミスは「怠慢」ではなく「脳の仕様」。
だからこそ、仕組みで支え、環境で防ぐ。
人を変えるより、構造を変える。
この考え方をチームに取り入れるだけで、組織の空気も、生産性も、驚くほど変わる。
そんな確信を与えてくれる本でした。
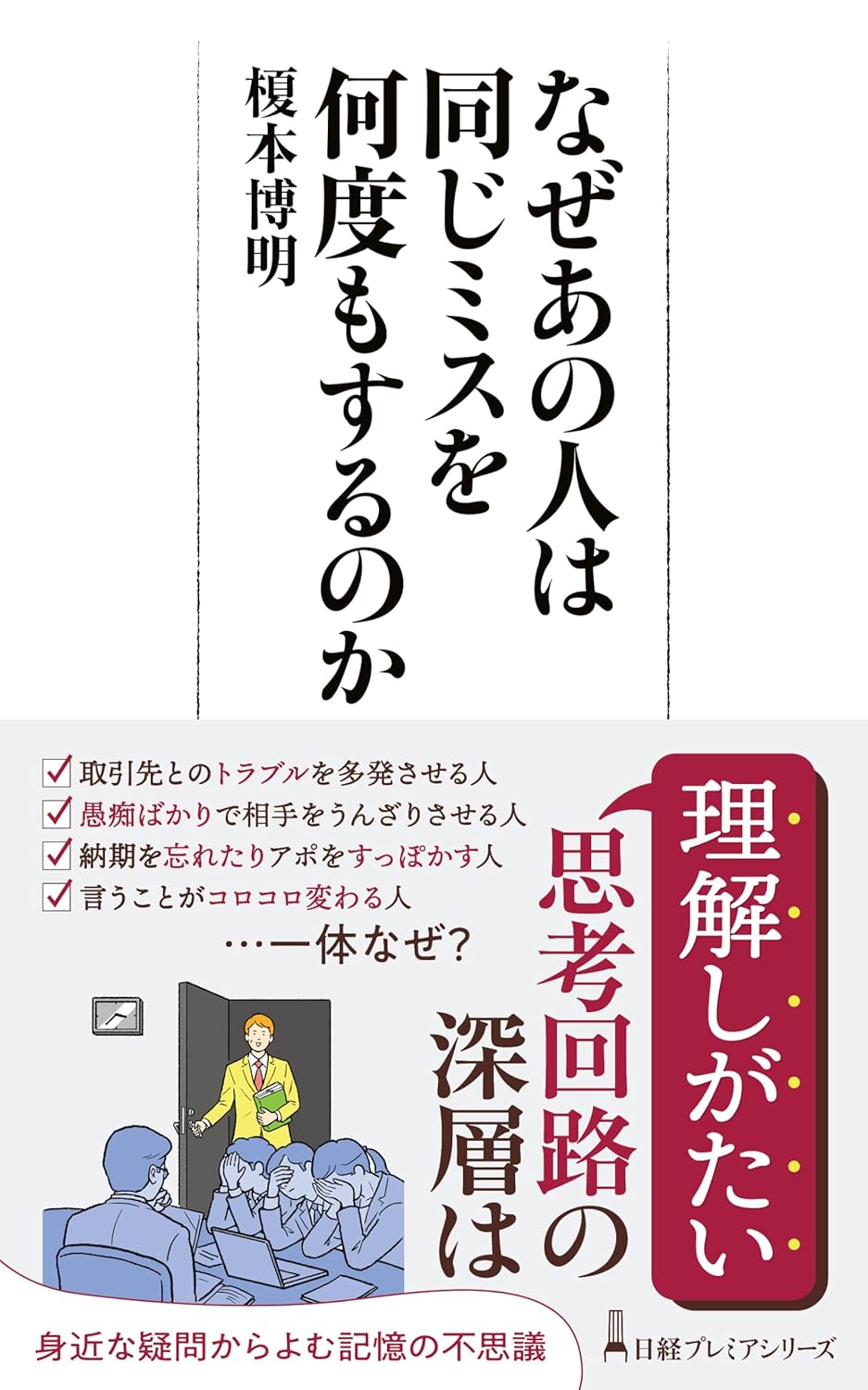

当社でも仕組みを改善することによって、パフォーマンスをあげることができました!これからも「ひと」を責めず、「仕組み」を改善することによってパフォーマンスをあげることを心がけていきたいと思いました!
音声解説 【読書感想】世界の一流は「休日」に何をしているのか? 越川慎司 著

soranoieはあなたにこんな未来を届けます
soranoieは、言葉とアイデアとデザインで、人やお店の魅力を丁寧に伝えるサポートをしています。
「伝わる」ことで、一時的ではなく、長く信頼される関係づくりが可能になります。
まずはお気軽にご相談ください。
ご相談は無料です。メールフォームからどうぞ!
折り返しご連絡させて頂きます。


